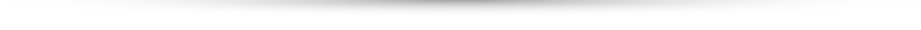卓越研究員事業は、新たな研究領域の開拓を目指す若手研究者に安定かつ自立した研究環境を提供することに対する、文部科学省の支援事業です。この事業では、大学などの研究機関からのポスト提示と若手研究者による卓越研究員への応募が行われ、最終的に研究機関と候補者の個別交渉で採用が決定されます。
この事業で提示されるポストは、テニュアトラック制あるいは一律任期制の雇用のものが一般的と思われます。ただし、本化学専攻では、通常の任期の定めのない助教・准教授ポストを積極的に本事業に提示していくことを予定しています。今後も、自ら将来の研究分野を切り開く気概を持った若手研究者の応募を期待しております。
平成29年度は、化学専攻から2つの助教ポストを本事業に提示し、その結果1つのポストについて、卓越研究員として井上賢一氏(現:物理化学講座有機物理化学研究室助教)を採用しました。
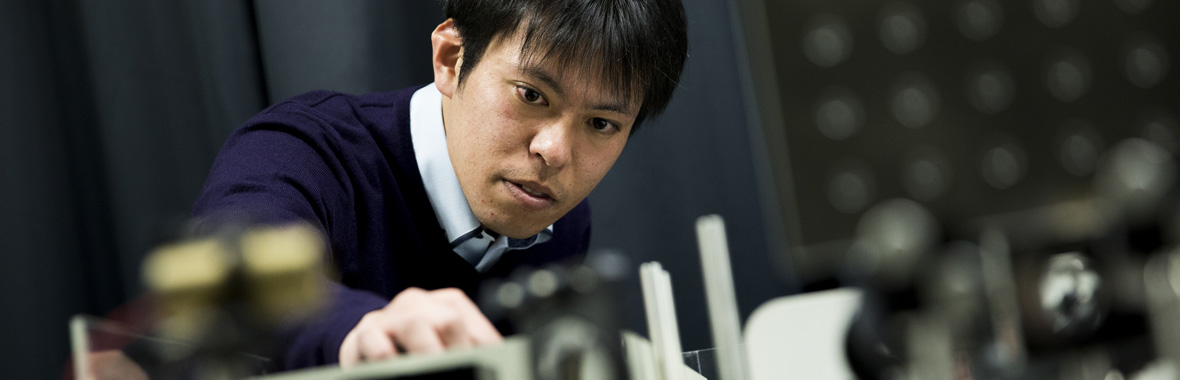
 井上氏は、2013年京都大学大学院理学研究科化学専攻博士課程(松本吉泰教授)を修了後、理化学研究所(田原分子分光研究室)での特別研究員・基礎科学特別研究員を経て、2017年11月1日より東北大学大学院理学研究科化学専攻に助教として着任しました。これまで、性質の異なる相の境界である「界面」に着目し、界面選択的な分光法である振動和周波発生分光法の位相分解測定・時間分解測定を用いて界面における分子の構造やダイナミクスの研究を行ってきました。卓越研究員事業では、光の回折限界を超える高空間分解能を備えつつ界面を選択的に測定することのできる分光法を新規に開発し、界面における反応機構を界面構造の観点から明らかにしていく予定です。
井上氏は、2013年京都大学大学院理学研究科化学専攻博士課程(松本吉泰教授)を修了後、理化学研究所(田原分子分光研究室)での特別研究員・基礎科学特別研究員を経て、2017年11月1日より東北大学大学院理学研究科化学専攻に助教として着任しました。これまで、性質の異なる相の境界である「界面」に着目し、界面選択的な分光法である振動和周波発生分光法の位相分解測定・時間分解測定を用いて界面における分子の構造やダイナミクスの研究を行ってきました。卓越研究員事業では、光の回折限界を超える高空間分解能を備えつつ界面を選択的に測定することのできる分光法を新規に開発し、界面における反応機構を界面構造の観点から明らかにしていく予定です。
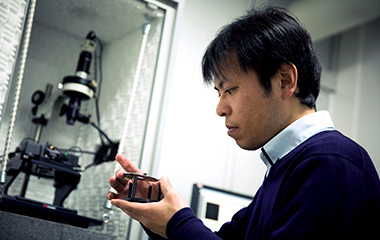 このようにして「きっかけは?」と聞かれても、おそらくはっきりとしたきっかけがあったわけではないと思います。気がついた時には化学を学びたい、化学者になりたいという気持ちで固まっていました。小さい頃から日常生活において様々な現象に「なぜ?」「どうして?」という疑問を抱くことがありました。それらの疑問の多くを化学は非常に論理的に説明してくれます。そして、化学的な視点に立つとこれまで見過ごしていたほんの些細なことにも自然の奥深さを再認識させられます。このような日常を新鮮なものにしてくれる化学に魅力を感じたからだと思います。
このようにして「きっかけは?」と聞かれても、おそらくはっきりとしたきっかけがあったわけではないと思います。気がついた時には化学を学びたい、化学者になりたいという気持ちで固まっていました。小さい頃から日常生活において様々な現象に「なぜ?」「どうして?」という疑問を抱くことがありました。それらの疑問の多くを化学は非常に論理的に説明してくれます。そして、化学的な視点に立つとこれまで見過ごしていたほんの些細なことにも自然の奥深さを再認識させられます。このような日常を新鮮なものにしてくれる化学に魅力を感じたからだと思います。
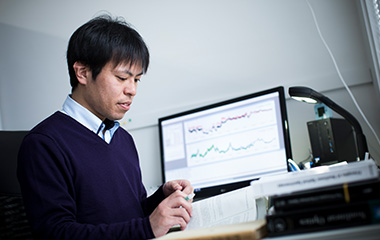 性質の異なる相の境界である「界面」に興味を持っています。界面の分子は、バルクと大きく異なる環境に存在します。その結果、界面は電気化学・生化学・有機化学などの様々な分野において重要な反応の場となります。これらの界面における反応を理解するために、物質の光に対する応答を測定する「分光法」を用いた研究をしています。特に、界面における反応活性とナノスケールの界面構造は密接に関連していると考えています。そこで、界面構造を識別できる高い空間分解能を持ちつつ、界面の分子の構造やダイナミクスを分子レベルで測定することのできる新しい分光法の開発を目指しています。ここから得られる知見を基に界面構造設計の指針を得ることができると期待しています。
性質の異なる相の境界である「界面」に興味を持っています。界面の分子は、バルクと大きく異なる環境に存在します。その結果、界面は電気化学・生化学・有機化学などの様々な分野において重要な反応の場となります。これらの界面における反応を理解するために、物質の光に対する応答を測定する「分光法」を用いた研究をしています。特に、界面における反応活性とナノスケールの界面構造は密接に関連していると考えています。そこで、界面構造を識別できる高い空間分解能を持ちつつ、界面の分子の構造やダイナミクスを分子レベルで測定することのできる新しい分光法の開発を目指しています。ここから得られる知見を基に界面構造設計の指針を得ることができると期待しています。
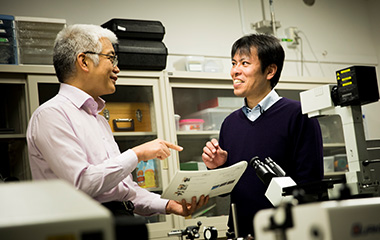 自分の研究を通して化学の発展に少しでも貢献していくことが目標です。現在の化学は、これまでの多くの先人の貢献によって築き上げられてきました。自分の研究対象である界面化学を例にとってもまだまだ未知の部分が多いので、貢献の余地は大いにあると思っています。未知の領域の本質的な理解につながるような既成概念にとらわれない研究をしていきたいです。
自分の研究を通して化学の発展に少しでも貢献していくことが目標です。現在の化学は、これまでの多くの先人の貢献によって築き上げられてきました。自分の研究対象である界面化学を例にとってもまだまだ未知の部分が多いので、貢献の余地は大いにあると思っています。未知の領域の本質的な理解につながるような既成概念にとらわれない研究をしていきたいです。
 東北大学は「研究第一主義」を掲げる大学です。表面だけの小手先の理解ではなく物事の本質的な理解を大事にしており、学問や研究にとってこの上ない環境であると言えます。化学を深く掘り下げて学びたい、最先端の化学研究をしてみたいという方は、東北大学理学部化学科できっと充実した学生・研究生活を送れると思います。
東北大学は「研究第一主義」を掲げる大学です。表面だけの小手先の理解ではなく物事の本質的な理解を大事にしており、学問や研究にとってこの上ない環境であると言えます。化学を深く掘り下げて学びたい、最先端の化学研究をしてみたいという方は、東北大学理学部化学科できっと充実した学生・研究生活を送れると思います。